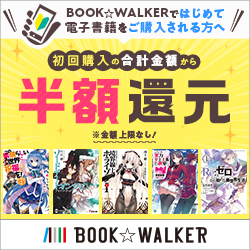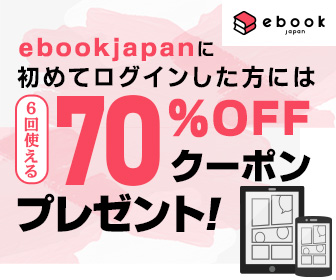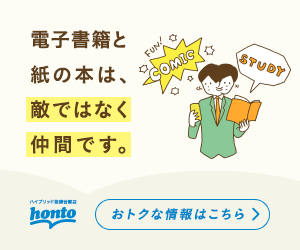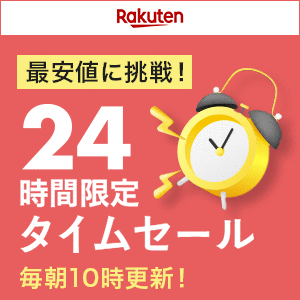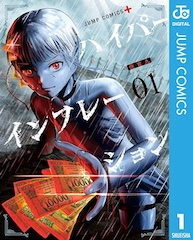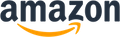【小説】『にんじん』
にんじん
ジュール・ルナール
『性根や気分は変わらんでも、家は変えられる』
いわゆる機能不全家庭、毒親を題材にした超古典小説だが、この作品の凄いところは感情没入的な説明や感情的な描写を一切そぎ落とし、最低限の客観的な事実と人物の行動の羅列のみで、閉鎖的な集団での特異なルール、抑圧や精神的迫害の支配する空気感、その渦中にいる人物たちの心理状態をこれ以上ないほど冷徹にリアルに再現しているところである。この主人公の母親は実の末息子である主人公に直接にあからさまな暴力や虐待をするわけではなく、たとえば他の兄姉を差し置いて一番きつい家事や汚れ仕事を「これ、やれるわよね」みたいな軽い雰囲気で当然のように押し付けたり、夜中に便器を隠してわざと失禁させて近所に言いふらしたり、デザートをさりげなくひとりだけ食べられないように仕向けたり、主人公が兄姉に怪我をさせられると何故が主人公の方が不注意だと責められたり、とか、現代の女子小中学生並みの幼稚かつ陰険なやり口で、気に入らない息子を家庭内のヒエラルキー最下層に追い込むのであるが、実にやりきれないのは、ターゲットである主人公自身も含めて家族みながそれらの異様な歪んだ状況を、自分たちの家庭の常識、当然の日常、空気として受け入れていて、その上でごく平穏に時に楽しく過ごし振る舞っているところである。そこには明確な悪意も敵意も一見存在せず、主人公の「にんじん」も家族たちからの仕打ちや態度を「またか、こんなもんか。どうせ俺だし」みたいにあえて疑問を持たず淡々と受け入れ、家族それぞれが自分の世界に引き籠もりながら日々を送っている。しかし、次第に近所のおじさんなどの「それはちょっとおかしいんじゃないか?」という突っ込みや、にんじん自身が寄宿舎生活で家庭を離れる機会が増えたことなどもあり、彼の中では次第に違和感や葛藤が膨らんでいき、終盤でついに正当な怒りを家族たちに向かって表明するのだ。それを切っ掛けにようやく父親とはまともな話し合いを持つにいたり、自分を虐げた「空気」の元凶を悟り、そして、自分の受けた扱いなり仕打ちなりは、自分自身の性質や振る舞いというのは実は大した要素ではなく、単なる「空気」による気まぐれな「役割」の押し付けにすぎない、ということを知るのだ。それにしても、この小説には予定調和な上辺だけの会話、いっけん饒舌でも噛み合わない対話や応酬、というものの実際がじつにリアルに分かりやすく提示されていたりする。
【マンガ】岡崎京子『pink』ほか
(2015/12/14 追加 2018/03/03 更新)

pink
岡崎京子

ヘルタースケルター
岡崎京子
96年に不慮の事故に見舞われ現在は休業中の岡崎京子。彼女が一線で活躍した80年代から90年代半ばにかけて、その作品は時代の「最先端」の流行なり趣味なり気分なりを鋭敏に反映したものとして、当時から現在に至るまで一部の文化人を含めたサブカルチャーの分野で高い評価を得てさまざまな批評や分析も膨大にされているのだが、あえて振り返って見れば、実は根底のテーマは至極シンプルかつ普遍的なものに思えるし、だからこそ現在も再版を繰り返され近年映画化もされたりしているわけだ。総じて岡崎作品に登場する若者たちというのは、一見最先端のファッションやカルチャーを享受して恋愛やセックスを気軽に楽しむ日常を当たり前のように過ごすという、『おそ松さん』の六つ子たちが言うところの「天上人」「リア充」なライフスタイルを謳歌しているように見えるが、そんな彼女ら彼らの本質は実は六つ子やトト子たちと大して変わらなかったりする。要はみな「大人」になることを恐れ、拒絶してひたすら刹那的な恋愛や娯楽に逃避し、モラトリアム生活を少しでも延長させようと足掻いているのだ。むしろ、生来の美貌や努力によってトップモデルとして成功しても、イケメンな彼氏やセフレ、高収入な伴侶に恵まれても、ホテトルや援交で手に入れた大金で着飾り散財しても、それらの何もかもが、結局は何一つ自分の現状を変えても未来を救ってもくれないことを身をもって知ってしまった彼らの方が、かえって六つ子たち以上にはるかに苦悩も絶望も深いといえるだろう。なお『おそ松さん』の雰囲気により近いのは80年代の作品なのだが、90年代から休業直前になるほどシリアスに「家族」や「暴力」そして「死」というテーマを掘り下げた作品が目立つようになる。代表作の『pink』『ヘルタースケルター』などは『おそ松さん』1期第10話の「レンタル彼女」や2期21話などで扱っていたテーマを極限まで描ききっている傑作であり、その点でもぜひ一読をおすすめしたい。
【マンガ】山岸凉子短編いろいろ
(2015/12/14 追加)
『おそ松さん』が過激不条理ギャグとして料理しているテーマをすでに容赦なく恐ろしいホラーとして表現し続けてきた筆頭といえるのが山岸凉子だろう。例を上げればキリがないくらいに傑作だらけだが、とりわけ有名な『天人唐草』をはじめ、家庭環境も含めて事情はどうあれ、いずれも自我が希薄で抑圧的で主体性に乏しいキャラクターがそれ故に陥る自己欺瞞と自己逃避の果てに、たいてい悲惨極まりない末路を迎えるという展開には正直なところ「なにもそこまで追い込まなくても……別に本人だけのせいというわけではないのに……」と少なからず釈然としない気持ちを抱いたりもするのだが、あえて読者の少女たちに衝撃を植え付けることでホラーでもファンタジーでもギャグでもない「現実」を生き抜くための喝を入れる、という作者なりの親心なのかもしれない。作者にとっては親の支配や家族の抑圧、そして世界の有象無象からの悪意というものは怪物や怨霊、魑魅魍魎、そしてサイコキラーに等しい存在であり、そこから逃れる術はもっぱら「自分の意志」しかなく、しかしそれでもなお逃げ切れる保証はないどころか少なからぬ犠牲が必ず伴う……というどう転んでもキャラクターや読者を決して幸福にはしてくれない残酷さ。いや、あるいはもっとも救済を求め、そのための手段を渇望しているのは他ならぬ山岸凉子本人だったのかもしれない。
【小説】ボリス・ヴィアン『北京の秋』ほか
(2016/04/02 追加)
北京の秋
ボリス・ヴィアン
心理には欠けているが、かわりにその欠けた部分を魂がおぎなっている。魂の入ったマリオネットでも、人を笑わせることは出来るだろう。だが笑った者は、その笑いに喉をつまらせ窒息する。
(全集版の安部公房の解説より)
赤塚不二夫以上にアナーキーかつタモリ以上にマルチな活動を繰り広げたフランスの作家、ボリス・ヴィアン。過去に何度か映像化され岡崎京子もコミカライズしている代表作『うたかたの日々』をはじめ、彼の遺した小説作品の多く、いやほぼすべての内容が「過激残酷青春ナンセンスギャグストーリー」の一言で終わらせてしまえるもので、その作品の主要人物は総じて社会生活と労働を徹底的に嫌悪し忌避し、ひたすら遊んで暮らすことを理想としその一方で異性との愛や恋を求めつつもいずれにも挫折し幻滅し、それこそ一生全力モラトリアム目指して身を投じながらも結局は何やかんやですべてに見放された挙げ句に全力バタンキューに至って愛も命も含めてすべてを失う、というような連中ばかりである。もっとも、最後の長編である『心臓抜き』に至っては主人公は破滅すらできずに、文字通り記憶も精神も空っぽのまま周囲の愚行や恥やらの後始末をしながら永遠の閉塞と停滞を余儀なくされたりする。『北京の秋』などはその最たるもので、とある計画(それは『おそ松さん』1期18話の主役争奪戦や最終回の「センバツ」の含意と相通じるものがある)のために、とある砂漠に各地各部署各属性から召喚された面々が、ある者は職務に没頭しある者は終日セックスに耽り、ある者は片思いに悶々とし、ある者はブラックホールへの飛び込み自殺を図り、それらの騒動の果てに何やかんやでそれらすべてが計画もろともにぶち壊され無と化し、ふたたびすべてが丸ごと繰り返されるのだ。私的には終始童貞思考ダダ漏れの自意識ライジングぎみなアンジェル青年の顛末が印象に残る。
砂漠は広広としている。故に、人はそこに集まりたがるものである。彼らは、ほかのいろいろなところでやっていたことを、そこでふたたびやりなおそうとする。砂漠でだと、そんなこともまた、日新しく見えるからである。砂漠は、何物をも鮮明に見せる背景となす。とりわけて、太陽が、特別な所有地を与えられていると仮定した場合にである。
(『北京の秋』本文より)
『北京の秋』/変幻自在な砂漠のライオン−ボリス・ヴィアン− 

(※詳細なネタバレを含む解説)
【小説】エミリ・ブロンテ『嵐が丘』
(2016/10/20 追加)
嵐が丘
エミリー・ブロンテ
言うまでもなく英国そして世界文学の名作であり、何度も映画化されている恋愛小説の代表的な古典の一つとしてその内容もあらすじも聞き知っている方は多いだろう。しかし、いざその原作を一読してみれば「身分違いの幼馴染みとの生涯を賭けた純愛」というロマンチックな雰囲気とはほど遠いもので、実際の展開をみれば揃いも揃って精神的に未熟で偏向し、徹底的に自己中で独善的でそれぞれ手前勝手な欲望と信念と強迫観念に取り憑かれた連中が、実社会とは徹底的に隔絶し閉塞した世界の中でほとんど身内同士の間でもって、それぞれのエゴと怨念と執着を剥き出しにしながらの拗れまくった愛憎と暴力の惨劇を徹頭徹尾、語り手も読者も完全に置いてきぼりにして繰り広げるという殺伐極まりないものである。とりわけ主人公ヒースクリフが少年時代のトラウマから、復讐と称して片っ端にひたすら常軌を逸した偏執と粘着ぶりでしかも大人げない逆恨みと碌でもない八つ当たりを終生撒き散らして、周囲の人間の生活を次々に破壊しまくり人生を潰しまくっていく暴虐ぶりと陰険さと狂気ぶりはまさにドン引き、というよりもはや常人には意味不明な領域にすら達しており、しかしそれらの所業はひとえに「愛」の存在によってなし崩しに免罪され「愛」の成就によってすべてが浄化されてしまうという理不尽極まりない結末。実際に彼らによって引き起こされる事件の数々は理不尽ギャグや不条理コントの趣きもあったりするのだ。むしろ「ギャグ」の世界やキャラクターが実体化してシリアスを志向すると、巻き込まれた当事者にとってはかくも悲惨な事態になるということか。その上で振り返ってみると、ひたすら「愛」が不在かつ不毛な世界で煩悩とルサンチマンを持てあまし軋轢を繰り返す『おそ松さん』の面々はある意味では『嵐が丘』の住人たち以上に救いのない生を生きているのかもしれない。
※名作だけあって、色んな訳や版が出ていますが、新潮の鴻巣友季子訳はイマイチです、非推奨
【小説】夏目漱石『吾輩は猫である』
(2017/01/27 追加)

吾輩は猫である (角川文庫)
夏目漱石
言わずと知れた大文豪・夏目漱石のこれまた言わずと知れた代表作にしてデビュー作だが、ある意味では漱石の作品のうちではもっとも内容題材ともに難解に拗れている話でもあると思う。それでも、一貫したストーリーやテーマが存在するわけではなくむしろコンセプトも設定も一見その時々の内輪ネタや時事ネタやパロディを放り込みつつ勢いで書き並べたような印象に加え、つまるところは「吾輩」の飼い主含めた当時のクソニートもとい「太平の逸民」こと時勢やシステムに乗り切れない微妙な負け組の面々が、それぞれ無駄に膨大なオタク的教養とライジング気味の自意識を持て余しながら「吾輩」の目の前で勝ち組連中への鬱憤や世間への不満や女への愚痴を好き勝手に垂れ流しながらダベりつつ傍目にはバカバカしい騒動や非生産きわまりない日常を延々と繰り広げるブラックコメディ、と見てみれば『おそ松さん』とも通じるものがあるかもしれない。しかしながらこの私には、夏目漱石のめぼしい作品というのは総じて半ニート若しくはニート的な連中が社会に対する鬱憤とミソジニーを上から目線でもって手前勝手に拗らせながら徹頭徹尾グダグダに展開してなし崩しの結末を迎えるような話ばかりで、この『吾輩』と『坊ちゃん』以外は正直どうにも面白いと思えないのだった(^_^;)。
【マンガ】原作:萩原天晴 /作画:橋本智広・三好智樹 『中間管理録トネガワ』
(2017/01/27 追加)

中間管理録トネガワ
萩原天晴 (著), 福本伸行 (著), 橋本智広 (著), 三好智樹 (著)
人気長期連載マンガ『賭博黙示録カイジ』のスピンオフギャグ作品として目下好評の『トネガワ』。原作での人気大物キャラクターに加えて、本編では没個性な役回りの集団にあえて焦点を当てそれぞれリアルな性格付けをほどこし、とりわけ現代の若い世代に共感しやすい個人として再生し、そして原作の世界観を踏襲し極力リスペクトしつつも一貫して現代風のシニカルな切り口で描きつつあくまで緩くマイペースに面白おかしく?展開していく、という手法において『おそ松さん』との共通点を勝手に見出したわけだが、その『おそ松さん』六つ子のような底辺無職の落伍者たちを搾取するブラック企業のエリートたち、世間的にはいちおう上層に位置する集団ではあるが、それでも内実は一部のマジョリティが無自覚に振り回すルールや手間勝手に設定変更されるラインに常に翻弄され、その結果として一般社会とは乖離した思想や価値観に無意識に囚われ、あるいは自覚しながらも逃れられず、かつそのような閉塞した環境においての視野狭窄な熱意や使命感、義務感による悲喜劇や悪意なきディスコミュニケーションの数々、しかしそうした状況下においても当人たちはそれぞれ至極ポジティヴかつ暢気?に日常をやり過ごしている……という要素などにも『おそ松さん』の面々と相通じる病理が感じられる、むしろ程度の差はあれども自分たちの異常性、特殊性や屈折をそれなりに自覚し焦燥や危機感も持っていたりする六つ子たちよりもある種の狂気において勝っているのでは……と考えてしまうのは私だけだろうか。
※アニメ版もキャストが超豪華でしたよ〜(ナレと演出は微妙……)
【小説】樋口一葉『たけくらべ』ほか
(2018/02/03 追加)

にごりえ・たけくらべ (新潮文庫)
樋口一葉
六つ子どもやトト子やチビ太と同年代にして不朽の名作の数々を生み出し、現在の紙幣の肖像にまでなっている天才作家・樋口一葉。その作品は広く知られているように、ほとんどが明治期前半の激動と栄光の時代から取り残され切り離され、前時代的な地縁血縁ほか現実社会の有形無形の圧力に束縛され、また自らもそれらの価値観に囚われてひたすら終わりなき閉塞、あるいは力尽きて破滅に向かう人々の苦悩と足掻きを描いたものである。その文体と手法は当時の一時代前すなわち江戸町人文学のそれに則っているが、扱っているテーマは当時のそして現代にもそのまま通じるあまりにもリアルな世代、階級、家族、そして男女の間の断絶と齟齬から生じる悲劇を等身大の限りない実感、共感とともに徹底した冷徹なまでのシニカルさで綴る。中でも代表作の『たけくらべ』は一見ノスタルジックで色彩あふれるムードの中、その実、明治の吉原界隈という「江戸」の残滓を引きずりつつ当世の「勝ち組」たちに寄生して辛うじて成立している小世界において刹那のモラトリアムを陽気に過ごすも、現実の世間や大人たちの思惑や価値観からは決して逃れることはできず、そのヒエラルキーやパワーゲーム、ホモソーシャル、ミソジニーなどの負の面をそのまま受け継いで反映してしまう子供たちの有り様は『おそ松さん』そして現代の若者たちにも充分に当てはまるだろう。しかし、否応なしにその世界の現実を受け入れて「大人」にならざるを得なかった『たけくらべ』や『わかれ道』の子供たち、あるいは容赦ない現実の中「ちゃんとした大人」になり損ねて落魄し狂っていった『にごりえ』『十三夜』などの男女たちに引きかえ、実家に寄生しながらでも徹底して「大人」であることの代償を回避しようと手を尽くす六つ子どもや「大人」の女としての犠牲をそのまま抜きに純然たる「アイドル」として勝ち組を目指すトト子の生き様は、時空次元を超えた『たけくらべ』の美登利や信如、正太といった一葉ワールドの子供たちそして女たちの復讐あるいはその代行の一種とも取れてしまうのは私だけ……かもしれないが。
———–