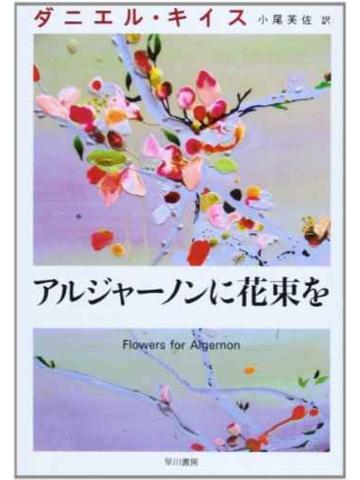前クールに山下智久主演で放映されていたドラマ『アルジャーノンに花束を』は、周知の通りダニエル・キイス作の同名の小説が原案のドラマである。かつて2002年にも同じくフジテレビで岡田惠和脚本で連続ドラマ化された方も私は観ている(しかし、あれからもう13年近くも経つとは……)。
(こちらはユースケ・サンタマリア主演の2002年版。こちらの方がストーリーは比較的原作に忠実だった)
しかし、以上のいずれもざっと観測した限りでは原作とはどうしても別物、という評価で、とくに原作読者からは手放しで絶賛、というわけにはいかないようだ。この作品に限らず小説やマンガの実写化というのは、その元のテキストや二次元での情報を三次元に再現する時点で、当然ながら専ら制作サイドによって膨大な量の情報を補完しなければならず、その過程でどうしてもすでに原作の読者それぞれの脳内に作られているイメージとの齟齬が出てくるし、それらを超えられるだけの魅力や世界観を構築しなければならないわけで、したがってオリジナルより却ってハードルがよほど高いのだが、それを知ってか知らずか、近年やたら実写化作品が濫発されてその度に大惨事になるという事態が繰り返されているわけだ。
アルジャーノンに花束を – みんなの感想 – Yahoo!テレビ.Gガイド [テレビ番組表]
(しかし、今期の「ど根性ガエル」は意外に面白い! ちなみに2002年版の『アルジャーノン』と同じ岡田惠和が脚本)
とりわけ、この『アルジャーノンに花束を』という作品の場合、まさに「小説」という形式でもってその世界観そのものが成立し、そしてテーマそのものが専らその手法に依存している。この小説に関してはまず、知能障碍者の青年チャーリー・ゴードンによる「経過報告」のみで構成される(特異な)文体が挙げられるが、『アルジャーノン』はこの徹底して主人公の「主観」で描かれているところが胆なのだ。これの読者はすべてを主人公チャーリー・ゴードンの視点からのみの情報で推測し、理解していくしかない。そして、その語られる情報の量と質とは当然ながら主人公の知能、精神の成長そして退行の度合いによって大きく左右されていくのである。
物語の初頭では、幼児の作文よろしくただ出来事のみを辿る即物的でたどだどしい文章から、読者は迷子から話を聞き出そうとする警官や店員のような気分でチャーリーの置かれた立場や状況を辛うじて推し量っていくのみだ。しかし手術によって、それまで言わば無知という繭に包まれていた彼の視界が次第に明瞭になり、それまで触れる術のなかった知識を感覚を次々に吸収し、世界も見識も急激に拡がっていく。彼をとりまく人々もはじめはただ存在と行動のみが示されるだけだったのが、彼の「進歩」によってそれぞれの表情や内面が詳細かつ繊細に描かれ、しだいに曖昧だった輪郭がくっきりしてくる。そして彼を取り巻く人間関係や背景の真相も、彼の理解にそのまま比例して読者にも明らかになっていくのだ。やがて彼の描写は回想の過去と現在、内面と外界がより複雑に交差しながら展開していき、彼によって綴られる世界はますます重層化、立体化してくる。とうとう彼が知性と精神の極限の高みに達し、しかしその刹那にその場所から急激に下降し、ふたたび彼の世界はたちまち無明の霧に包まれ、彼をめぐる人々もまたその造形がぼやけ霞んでいき、彼の世界からも読者からも遠ざかって行く。ついには彼の精神は静かに涅槃のあわいに溶け込み、存在そのものも読者の視界から消え去っていく……。これらすべて、もっぱら「彼」の側から表現しつくされていることだ。
こうした手法によって、読者は例外なく否応なしにチャーリー・ゴードンその人への視点、彼自身のあらゆる感情をそのまま己のそれと重ね合わせ、一体化させられてしまう。冒頭からチャーリーが長い長い「子供」時代から徐々に抜け出して成長し、始めて得るさまざまな経験や知識にともに胸をときめかせ、やがて彼に自我が生じ、羞恥心、自尊心が芽生え、他者の心の裏表を知り、憎悪や嫉妬を知り、性のアンビバレントについて葛藤し苦しみ、そして恋に揺れ動き愛を知り、ついに神の境地すら垣間見て、そしてその場所からたちまち崩れ落ち、それまでに獲得し、積み上げてきた知識、感情、記憶、体験のすべてをみるみる喪なっていく恐怖と絶望をまるで我が事のように実感させられる。読者一人ひとりがジェットコースターに括り付けられた客のようにチャーリーの劇的な上昇と下降のドラマ、人生そのものを、否応なしに追体験されられるわけだ。そして、件のラストの一文を読み終えたころには、完全に「彼」の感情、精神、人格そのものと己のそれとが同一化して、「彼」の喪失と諦念、そしてある種の悟りの境地をそのまま我が事のように感じ取り、涙するのだ。
しかし、いざこれらを映像として再現するとなると、視聴者には初めから「彼」が見ている世界以外、本来ならいまだ彼が知らず、今後に彼が知るであろう情景も(客観的視点での)カメラの視角に捉えられ写されて、彼の周りの人物たちの有り様も含めて元から提示されることになる。「彼」ひとりの主観で成り立っていたはずの原作の世界とはその時点でずれが生じてしまうのだ。まして連続ドラマとなれば、「彼」以外の人物にも元から詳しい背景や設定をあらかじめ用意して説明しておかなければならないし、キャストの見せ場を用意する意味でも、「彼」が見えず、そして居ないはずの場所であってもその行動や心理を視聴者には見せて伝える場面を作らなければ作品として成立させられないわけだ。したがって、視聴者は「彼」への一体化ができずに「彼」をあくまで画面の向こう側の映像世界に生きる人物たちの一人、として捉えざるを得なくなる。よって原作小説ならではの読者への吸引力、魅力であったものが大きく損なわれてしまうし、そして、テーマも世界観もおのずと変化や調整を強いられるのである。
……とは言え、先掲のドラマと言えば、以上に述べたように原作とは完全に異質であり別物ではあるのだが、あくまで「別物」のドラマ作品としては、実は結構良くできていたように思うのだ。原作では個人および人間が生きる上で生じるあらゆる要素や局面をチャーリー一人に象徴させて描いているのだが、今回の2015年版ドラマの方は、まさに連続ドラマの特性を利用してあらかじめ思い切って群像劇として設定し、彼らそれぞれの視点や行動でもって主人公・咲人の生き様や心の揺れを浮かび上がらせるという、原作とはあえて真逆の手法を採っていて、そしてそれはある程度成功していたと思える。原作では女性像がやや類型的、とりわけヒロインのアリス・キニアンは理想化されすぎているきらいがあるが、ドラマではヒロイン・遥香をはじめとする女性たちは独占欲や保身なども含めてそれぞれ生身の等身大の女性として描かれていたところも好感が持てた。
それでも、原作では主人公とは断絶したままで終わる母親との関係はやはり美化されているし、原作におけるラストのチャーリーの退行は明らかに老衰、そして死のメタファーであるのだが、ドラマの方ではいずれも主人公のそれをふたたびかつての「(純真無垢な)子供」へと戻る、というように解釈をあえて変え、希望と救いの感じられるラストに導いている。しかしそれだと、もう一方の重要キャラであるはずのアルジャーノンの存在と死、そしてあのラストの一文の重みと意味合いが薄れてしまうのだ。原作においては最後にアルジャーノンに献げられるはずの「花束」は、ドラマにとっての「愛」や「希望」の象徴ということに留まらず、そのままチャーリーへの弔いの花であり、彼からそれまで生きてきた世界への永訣の印だからだ。一度はあらゆる愛や知識を得た世界、それらを与えてくれた人々との絆をあえて全て断ち切ってひとり旅立ち、それでも新たな世界で残された時間を愛と希望を持って生きようとする決意が、彼が僅かに残された理性から絞り出したあの一文に込められ、そして原作のテーマ全てが凝縮されているのだ。
もっとも、仲間たちとともに新たな場所で再生して生きていくというドラマの晴れやかな結末も、いち視聴者としてはもちろん救われるし大いに歓迎したいのだが、原作でのチャーリーの終始壮絶かつ孤独な、そしてそれでも最後まで尊厳と愛を持って生きた軌跡のインパクト、そこから生じるカタルシスにはやはり及ばない。あるいは、それも含めて、制作者サイドもそのことを充分に承知していたからこその改変なのだろう。それでもやはり視聴率はあまり良くなかったようで、やはり映像化には向いていない作品なのだろう。
アルジャーノンに花束を
ダニエル・キイス (著),